突然ですが、問題です!「最高の伸びとコシのあるお餅」を作りたい時、一番適したもち米は次のうちどれでしょう?
- ヒメノモチ
- はくちょうもち
- こがねもち ……答え、すぐに分かりましたか?( *´艸`)
もし「うーん…」と悩んでしまったなら、もったいない!せっかく手間ひまかけて作るもち米料理、品種選び一つでその仕上がりが天と地ほど変わってしまうんです!
でも、安心してください!
この記事を読めば、そんなもち米選びの〝疑問〟が、すべて〝納得の答え〟に変わります。
そこで本記事では、クイズの答えはもちろん、『代表的なもち米の種類と、料理が美味しくなる選び方の秘訣』を、どこよりも分かりやすく徹底解説いたします!
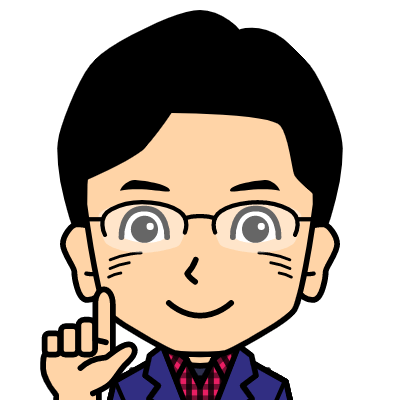
この記事はこんな方にオススメ
この記事を最後まで読んでいただければ、あなたはもう「もち米マスター」!もち米選びで迷うことはありません!
作りたい料理に合わせて迷わず最適な一袋を手に取り、誰もが「美味しい!」と唸る一品を作れるようになっていますよ!(^^)
※いち早く内容を知りたい方は「目次」より読み飛ばして下さい。
【用途別】もう迷わない!料理が最高に美味しくなるもち米の種類


せっかく手間ひまかけてもち米料理を作るなら、最高に美味しく仕上げたいですよね!実は、もち米にも料理との「相性」があるんです!
このセクションでは、あなたの作りたい料理を格上げする、運命の品種選びをナビゲートします!
※あくまで当サイトの見解ですので、ご了承ください。
お餅/お雑煮用|最高の伸びとコシを求めるならこの2品種
ズバリ!最高の伸びとコシを誇るお餅を作りたいなら『こがねもち』と『わたぼうし』が最強のタッグと言いたい!( ̄ー ̄)


この2つの品種は、もち米の中でも特に粘りとコシが強く、しっかりとした弾力が特徴。だから、お餅にしたときに、あのたまらない「びよ〜ん」と伸びる食感と、噛みごたえのある満足感を実現してくれます。
煮崩れしにくい性質も持っているため、お雑煮やお汁粉に入れても形が崩れず、もち米本来の豊かな風味を最後までしっかり味わえますよ!(^^)
赤飯/おこわ用|粒感をしっかり残すならこの品種がおすすめ
赤飯やおこわで大切な〝一粒一粒の存在感〟いわゆる粒感を活かすなら、『ヒメノモチ』が断然おすすめです!


ヒメノモチは、粘りがありながらも比較的あっさりとした風味で、炊き上がりの粒がしっかりと独立するのが最大の魅力。
この特徴のおかげでベチャっとせず、口の中でホロリとほどけるような上品な食感のおこわや赤飯に仕上がります。
具材の味付けを邪魔しないので、素材の風味を主役にしたい五目おこわなどには、まさに理想的な品種と言えるでしょう!(≧▽≦)
和菓子/大福用|冷めても柔らかさが命のもち米はコレ!
大福やおはぎなど、時間が経ってから食べる和菓子には、冷めても柔らかさが持続することが何よりも重要ですよね!
そんな和菓子作りの救世主となるのが、北海道生まれの『はくちょうもち』です!


この品種は、炊いた後の柔らかさが長持ちするという、素晴らしい個性を持っています。
だから、時間が経っても硬くなりにくく、絹のようになめらかな口当たりの大福やおはぎを作ることができるんです!
粘りも非常に強いためおこわにも向いており、和菓子やおこわなど、幅広い用途でその柔らかさを保ちます。プロの和菓子職人さんにも愛されるその魅力を、ぜひ一度ご家庭で実感してみてください!
【一覧表】ひと目でわかる!用途別もち米品種マトリックス
「結局、私にはどれがいいの?」そんなあなたのために、ここまでご紹介した品種の特徴を一覧表にまとめました!
この表を見れば、あなたの目的にぴったりのもち米が、きっと一瞬で見つかりますよ!
| 品種名 | 最適な用途 | 粘り | コシ | 甘み | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| こがねもち | 餅、雑煮、お汁粉 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | **東の横綱!**煮崩れしにくい |
| わたぼうし | 餅、おこわ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | 白くふっくら美しい仕上がり |
| ヒメノモチ | 赤飯、おこわ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 粒感が良くあっさり上品な味 |
| はくちょうもち | 和菓子、大福 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | 冷めても驚きの柔らかさ! |
| ひよくもち | 万能(餅、おこわ) | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 九州代表!冷めても硬くなりにくい |
| 滋賀羽二重糯 | 餅、高級和菓子 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 幻の最高級品!格別の味わい |
あなたも今日からもち米通!人気6大品種の特徴を徹底比較


品種ごとの特徴やストーリーを知ると、もち米選びはもっともっと楽しくなります!
このセクションでは、日本を代表するもち米とも言える、個性豊かな6つの品種の特徴を深掘りしていきましょう!
ちなみに、北海道名寄市はもち米の作付面積・生産量で日本一を誇り、名寄産のもち米は伊勢名物『赤福』や全国の銘菓、ロッテの『雪見だいふく』などに使われるなど、その品質は高く評価されています。
最高峰ブランドの一つ!東の横綱「こがねもち」の魅力
「東の横綱」とも称される『こがねもち』は、その高いコシと伸び・豊かな風味から、粘りとコシが特徴の品種の代表として「もち米の王様」と呼ばれることもある、新潟県生まれの最高峰ブランドの一つです!


その最大の特徴は、なんと言っても力強い粘りとしっかりとしたコシ、そして豊かな風味の三拍子が揃っていること。
お餅にすれば、絹のようになめらかで、どこまでも伸びていくような最高の食感を楽しめます。
煮崩れしにくいのでお雑煮にも最適ですし、赤飯やおこわにしても、その存在感はまさに主役級と言っても過言ではありません!
どんな料理も格上げしてくれる、頼れるオールラウンダー的なお餅です!
上品であっさり!名脇役「ヒメノモチ」の万能性
全国で広く栽培され、多くの人に愛されているのが『ヒメノモチ』です。


最高峰「こがねもち」が主役なら、ヒメノモチはどんな料理にもそっと寄り添い、その魅力を最大限に引き出す名脇役!
その特徴は、上品であっさりとした味わいと、炊き上がりの粒立ちの良さにあります。
なので、素材の味や繊細な味付けを活かしたい赤飯やおこわに使うと、それぞれの具材の風味が際立ち、全体の調和がとれた素晴らしい一品に仕上がりますよ(^^)
冷めても硬くなりにくい!九州代表「ヒヨクモチ」
九州地方、特に佐賀県で大切に育てられているのが『ひよくもち』。


この品種の最大の強みは、なんと言っても「冷めても硬くなりにくい」という素晴らしい特性にあります!
炊きたてはもちろんモチモチで美味しいのですが、時間が経ってもその食感が落ちにくいんです。
お弁当に入れるおこわや、作り置きしておきたいおはぎなど、時間が経ってから食べるシーンでその真価を最大限に発揮します!きめ細かく上品な甘みも魅力の一つですね(^^)
絹のような柔らかさ!和菓子に最適な「はくちょうもち」
北の大地、北海道が誇るもち米のエースとも言えるのが『はくちょうもち』です。
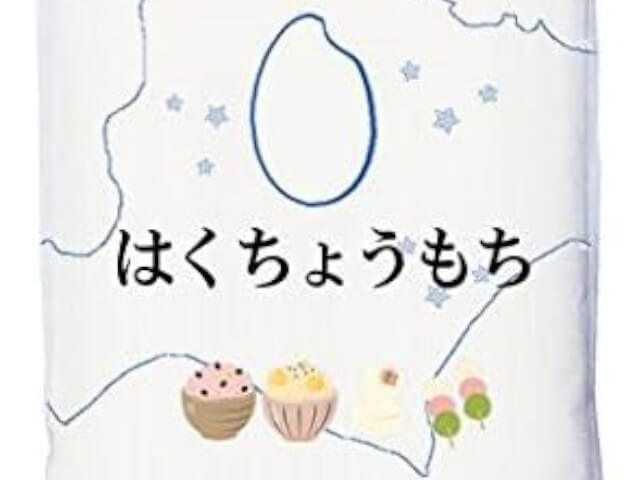
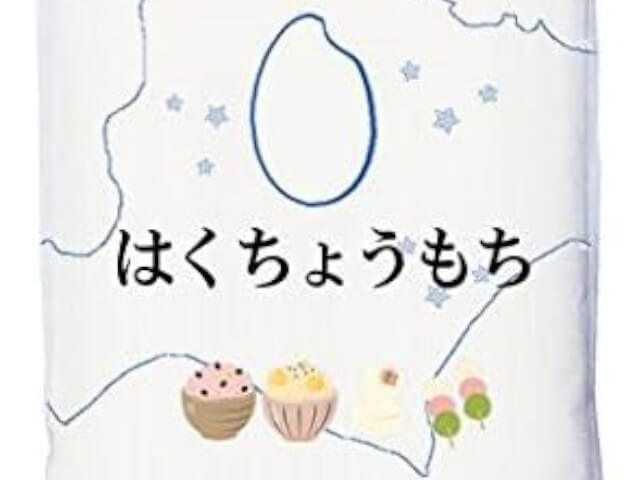
その名の通り、白鳥の羽のように白く美しい見た目と、絹のようになめらかで柔らかい食感が特徴。
特筆すべきは、冷めてもその柔らかさが長持ちすること!この性質が、大福などの和菓子作りには欠かせない存在となっています。
しかし、その魅力は和菓子だけにとどまりません。粘りも非常に強いため、おこわにしても絶品!家庭用の炊飯器でも美味しく炊ける手軽さも、嬉しいポイントですよね(≧▽≦)
真っ白で美しい!ふっくら搗きあがる「わたぼうし」
「こがねもち」と並ぶ新潟県の二大巨頭、それが『わたぼうし』です。


その名の由来は、花嫁さんの綿帽子のように、白くふっくらと美しいお餅に仕上がること。
搗きあがりの純白の美しさは、見る人の心を奪うほどです!もちろん、見た目だけでなく味も一級品。
しっかりとしたコシの強さと、噛むほどに広がる豊かな甘みが特徴で、焼いたときの香ばしさはたまりません!お祝いの席を華やかに彩るお餅に最適ですよ!
幻の高級品!格別の甘み「滋賀羽二重糯」
数あるもち米の中でも最高級品と称され、まさに“幻”とも言われるのが滋賀県産の『滋賀羽二重糯(しがはぶたえもち)』。
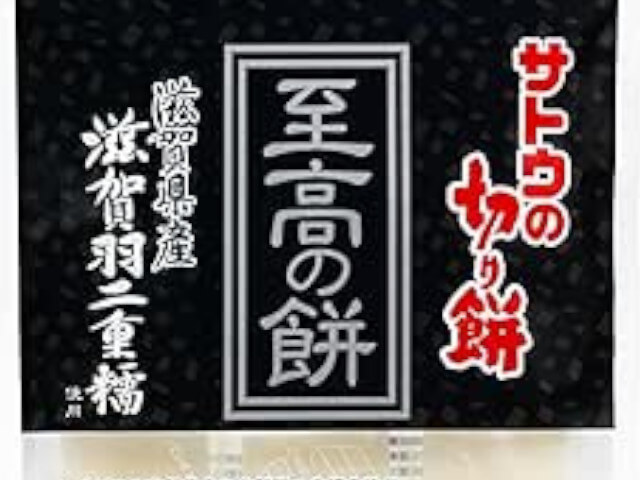
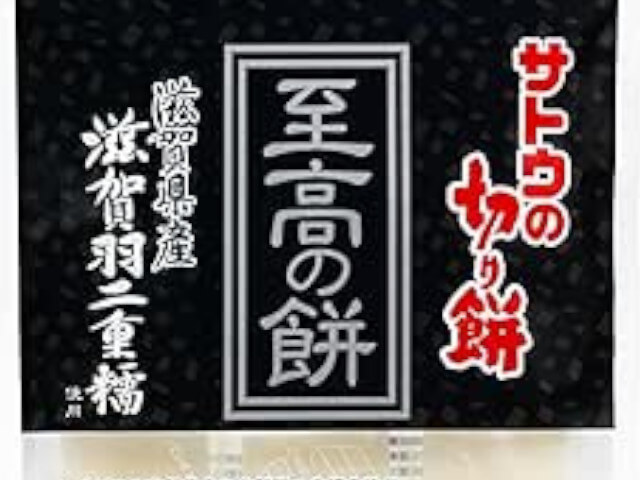
生産量が少なく非常に希少で、その特徴は他とは一線を画す、驚くほどの伸び・きめ細かく甘みのある特級の味わいにあります。
「一度このお餅を味わってしまうと、他のお餅には戻れない…」と言われるほどの格別の美味しさがあります!
特別な日のお祝いや、大切な人への贈り物として選べば、感動を呼ぶこと間違いなしの逸品ですよ!
今さら聞けない!もち米とうるち米の3つの違い


ところで、「もち米」と私たちが普段食べている「うるち米」って、具体的に何が違うのでしょうか?
そんな素朴な疑問も、ここでスッキリ解決しちゃいましょう!知ればもっとお米が好きになりますよ(^^)
秘密はデンプン!粘りの元「アミロペクチン100%」とは?


あの独特な粘りの秘密は、ズバリ!お米に含まれる「デンプン」の種類と割合にあります!
デンプンには「アミロペクチン」と「アミロース」の2種類があり、粘りの元となるのがアミロペクチン。
驚くべきことにもち米のデンプンは、このアミロペクチンがほぼ100%!だから、あれほど強く粘り、モチモチになるんです!
一方、うるち米はアミロペクチンが約80%、アミロースが約20%。このアミロースの存在が、冷めるとご飯が硬くなる原因なんですね。
【写真で比較】炊きあがりの見た目と食感はこんなに違う


もち米とうるち米は、炊く前の見た目からして違います。
うるち米が半透明なのに対して、もち米は光を通さない不透明な乳白色をしています。これはデンプンの構造の違いによるもの。
そして炊き上がりは一目瞭然!うるち米は一粒一粒がふっくらしているのに対し、もち米は粒同士がしっかりとくっつき合い、ツヤツヤと輝いています。
この見た目の違いが、口に入れたときの「あっさり」と「もっちり」という、食感の決定的な違いを生み出しているのです。
腹持ちが良いのはどっち?カロリーと栄養価の比較


実は、もち米とうるち米のカロリー自体に、大きな差はありません。
しかし、多くの方が「もち米の方が腹持ちが良い」と感じるのは事実です。その理由は、消化吸収のスピードにあります。
粘り気の強いアミロペクチンは、胃の中での分解がゆっくり進むため、消化吸収が穏やかになります。
その結果、満腹感が長く続き、腹持ちが良いと感じるのです!エネルギーが長持ちするので、古くからお祝いの席や力仕事の前に食べられてきたのも納得ですね(^^)
もっと美味しく!もち米選びが楽しくなる豆知識3選


ここまで来ればあなたも、もち米マスターに一歩近づきましたね!(^^)
最後に、知っていると食卓での会話が弾むこと間違いなしの、とっておきの豆知識を3つご紹介します!
日本三大もち米とは?産地ごとのこだわりと歴史


もち米の名産地として、北海道、佐賀県、そして新潟県は「日本三大もち米処」として名高い産地です!
例えば、米どころの新潟県内では、きれいな水と寒暖の差がある魚沼地方のもち米が、特に味や粘りが良いと言われています。
佐賀県では温暖化に対応するため、田植えの時期を調整するなど、『ひよくもち』の品質を守るための弛まぬ努力が続けられています。
それぞれの土地の気候風土と生産者の方々の熱い想いが、最高のもち米を生み出しているんですね!
初心者でも失敗しない!炊飯器で炊く3つの黄金ルール


「もち米を炊飯器で炊いたら、べちゃっとして失敗した…(-_-;)」そんな経験、ありませんか?
実は、3つの黄金ルールを守るだけで、誰でも簡単にお店のようにもち米を炊けるんです!
もち米を炊飯器で炊くときは、いくつかのコツがあります!
- 水加減を調整する!:もち米は普通のうるち米よりも粘り気が強いため、うるち米を炊くときよりも水加減を10~15%ほど減らすと、柔らかくなりすぎずに美味しく召し上がれます。
- しっかり吸水させる!:もち米はうるち米より水を吸いにくいため、調理時には4〜5時間水に浸すなど、吸水時間を長めにとりましょう。
- 蒸し器を使うのもおすすめ!:炊飯器だけでなく、水に浸した後、水切りしてから蒸し器で30〜40分ほど蒸すと、もちもちとした食感が際立ちます。
これらのポイントに注意して、美味しいもち米料理に役立ててください。
【Q&A】水稲もち米と もち米の 違いはなんですか?


お店で〝水稲もち米〟という表示を見て、「普通のもち米と何が違うの?」と疑問に思ったことはありませんか?
ズバリ!答えは「ほとんど同じ」です!(^^)
「水稲(すいとう)」とは、水田で栽培されるお米のことを指しますが、日本で市販されているもち米のほとんどは水田で栽培されているため、「水稲もち米」と表記されていることが多いのです。
つまり、私たちが普段「もち米」と呼んでいるものと同じと考えて大丈夫!これでスッキリしましたね!(≧▽≦)
【まとめ】食卓を彩る「絶品もち米」を見つけよう!
今回は、奥深い『代表的なもち米の種類と、料理が美味しくなる選び方の秘訣』について、ご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?
一言でもち米と言っても、その品種ごとに豊かな個性があり、それぞれに得意な料理があることを、きっと感じていただけたと思います!
改めて、この記事のポイントをまとめると以下の通り。
- お餅・お雑煮なら、最高峰の「こがねもち」や白く美しい「わたぼうし」。
- 赤飯・おこわなら、粒感が命の「ヒメノモチ」。
- 和菓子なら、冷めても柔らかい「はくちょうもち」。
- 万能選手を求めるなら、九州の「ひよくもち」。
- 特別な日には、幻の「滋賀羽二重糯」。
これでもう、スーパーのもち米コーナーで立ち尽くすことはありませんね!(^^)
大切なのは、あなたが「何を作りたいか」「どんな食感が好きか」をイメージすること。
本記事を参考に、あなたの料理を最高に輝かせてくれる「絶品もち米」を、ぜひ見つけてみてください!
あなたのもち米ライフが、もっと豊かで美味しいものになることを、心から願っています!
『もち米の種類はどれがいい?もう迷わない用途別おすすめ品種6選』を、最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!
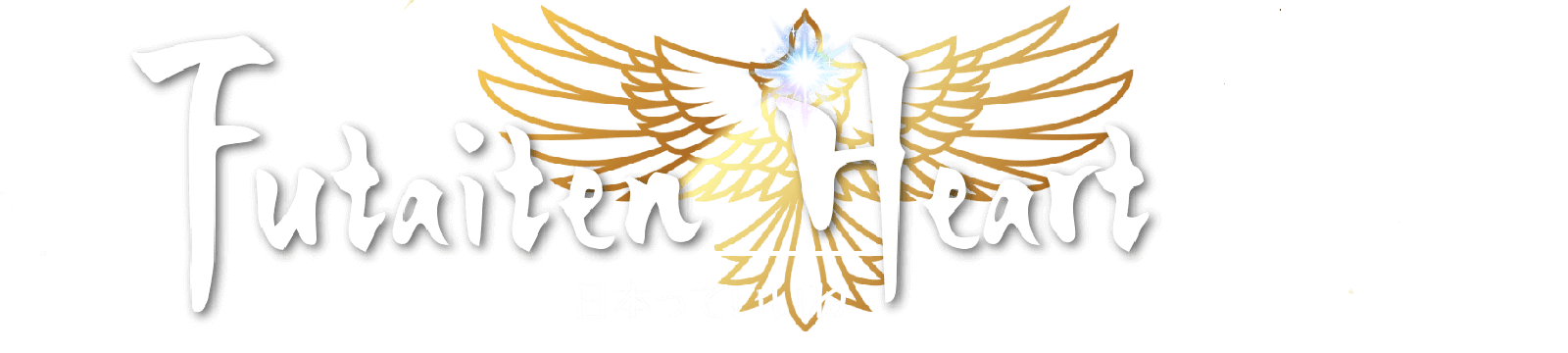


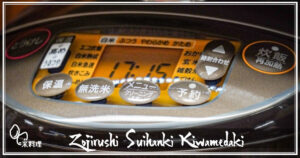






コメント